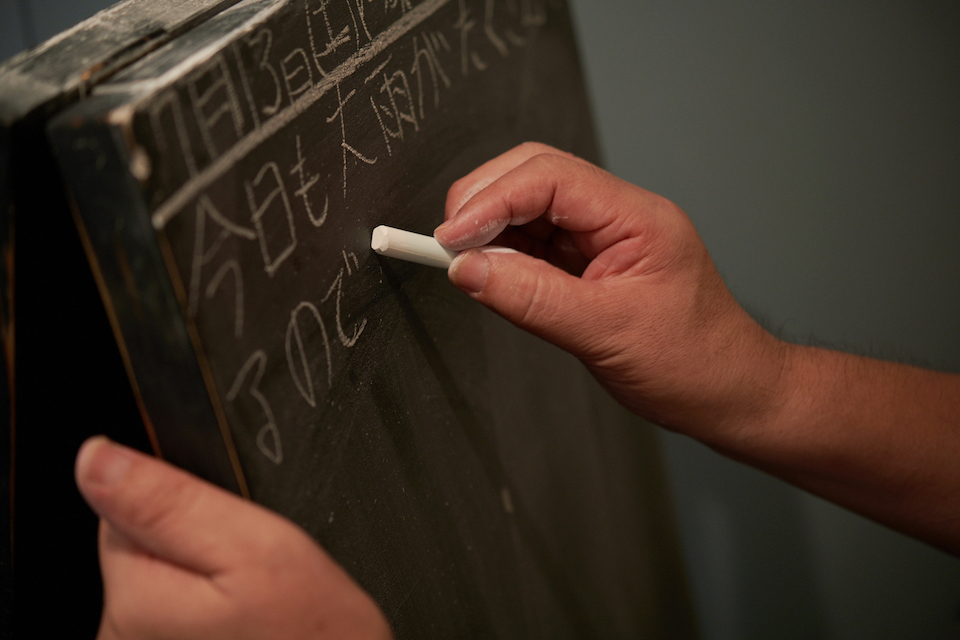アートは特別な能力がある人だけのものではない。鹿児島県の〈しょうぶ学園〉での創作活動に触れ、できあがった作品や製品を見ていると心底思う。
ひたすら削るのが好きな人の削り跡をそのまま活かした器や、こねあげた粘土でリズミカルに形成されたオブジェ、裏を返すと色とりどりの糸が長いまま残った刺繍のシャツなど、その人の得意なこと、楽しんでやっていることをそのまま活かした結果、完成した作品や製品は非常にアート的。手の動きや、制作過程を楽しんでいる様子までもが伝わってくるようで心動かされる。
〈しょうぶ学園〉の活動は、工芸・芸術・音楽・食と多彩な広がりをもっている。施設内で、野菜づくり・販売が行われていたり、パン工房、カフェ、そば屋があったりと、施設外の人とも場を共有できる。 (2020年4月より当面の間、新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、一般の方の施設の立ち入りは禁止、レストラン、パン屋、そば屋、ギャラリーは営業休止)。
そうした広がりをもった活動の中、利用者たちの制作の柱となっているのは「布の工房」「木の工房」「土の工房」「和紙/絵画造形の工房」という4つの工房。魅力的なプロダクトは、どういう環境で、どのようにつくられているのだろう。これらの工房を案内してもらった。
ボタン、カトラリーから家具まで手がける「木の工房」。
とんとんとんかんかん。心地よい音がリズミカルに鳴り響く「木の工房」では、風が吹き抜ける広々とした場所が作業スペース。それぞれが木槌や鉋などの道具を手にして、削ったり、彫ったりを自由に行っている。扱っている木材にクスノキがあるので、爽やかな香りも漂っている。
「基本、こちらでは彫りの作業をする利用者さんが多いです。目印をつけた木を自由に彫っていく作業です。彫り終えたら職員が成形してお皿の形にしたあと、塗装をかけて仕上げていきます」と、デザイン室統括主任の榎本紗香さんは説明してくれる。


〈しょうぶ学園〉が「ものづくり」へとシフトした最初の一歩が、「木の工房」の前身となる「木工班」で、1983年頃、現統括施設長の福森伸さんが「民芸」に憧れ、2〜3人の利用者とともに始めたのがプロダクト制作のスタートだった。
「最初は、“できるだけはみださず、きちんとしたものをつくりましょう”と、ちゃんとできる人だけに手伝ってもらっていました。それ以外のできない人はお遊びチーム。でもしばらくやっていくと、そのお遊びチームの“ずれている”とか“僕らと違う”ということこそ、“新しいものづくり”かなって思うようになっていくんです」と福森さんは振り返る。
よそ見をしていて、一方だけ多く削れてしまったり、角は取らないといっても削りとってしまったり、きれいに仕上げたいのに、釘で傷をつけてしまったりということが、日常的に起こっていた。
「それを、“うまくできない”と考えるのではなく、角を取ってばかりいるなら、その人自身が“角をとる人”になればいい。傷ばかりつける人は、“傷をつける人”になり、それを活かした作品をつくりましょうと。そうしていくうちに気づいたのは、釘で傷をつけたあとに漆塗りをした酒器と酒膳で飲む酒がめちゃくちゃうまいこと」と福森さんは笑う。
こうして自分たちの制作方法、作業の道すじを「発見」したことで、利用者と職員の関係もずっとよくなったという。
「それまでは、お互いがすごく苦しかった。教えてもできないし、教えられるほうも、がんばりますとはいうけれど、やっぱりできない。でも、このやりかたにしたら、ものづくりにおける“間違い”がなくなった。もちろん、生活では“寝ない”“食べない”などしちゃいけないことがあるから、職員はケアをしないといけない。でもそれとこっちの世界は別。“ものづくり”でケアをする必要はないから、向かないことはしないほうがいい。それだけことだと気づきました」。

現在、13~15名が所属していて、職員3人が担当する「木の工房」。

工房の奥では、からんころんと小気味良い音をたてながら、木の箱を回している人がいる。 「米山宜秀さんは、今日はボタン職人なんです」と榎本さん。
いらなくなった板を小さく切って木っ端にして、内側にやすりを貼った箱の中にいれる。その箱をひたすら回し続けると、いつの間にか角がとれて手触りのいい木っ端ができる。それを加工してボタンにするという。
「施設長がよく言うのは、“利用者はそのままで、職員が考えて工夫しろ”ということ。社会的に良いとされていない行為でも、作業の手順や、製品と行為の関係性を変えることで、おもしろいものが生まれてくるようになりました。職員もがんばっています。ものづくりをしたことがなくても、お箸一本から始めて、今では家具をつくれるようになった人もいるんです」と榎本さん。
ボタン職人の米山さんは、ボタン制作だけでなく、木彫も立体作品制作も、漆も塗れるマルチ・プレイヤーだというので、どの制作が一番好きか質問してみた。すると、迷わず「これ」と、ボタン回し機を指してにやりと笑った。
こねたり、まるめたり、のばしたり。遊びの中から生まれる「土の工房」。
次に訪れた「土の工房」には、建物の前や入ってすぐのスペースなど、いたるところにオブジェやお面、器などがざっくばらんにおいてある。ここでは、こねたり、まるめたり、のばしたり、積み上げたり、削ったりなど、利用者たちが土と遊んでいくなかから、作品を生み出しているという。
「この工房には団子職人もいるし、キリン職人もいるんです」という榎本さんの解説を聞いて見渡すと、ろくろを回して器をつくっている人、絵付けをしている人、こねた粘土からリズミカルに作品を生み出している人など、自由に制作活動が行われていた。 長い脚の上に器がのったオブジェをたくさん作っている様子が目に止まった。
「中田麻美さんがつくっているこの脚付き鉢は、評判がよかったので、私たちがお願いして量産してもらっているんです。彼女の動きって、とてもリズミカルですよね。手先をぴんと伸ばしながら、粘土をきれいに伸ばしていく。見ていて楽しい動きでつくっているから、オブジェの脚先も楽しく見えるんでしょうね」

脚付き鉢を制作する中田麻美さん。


〈しょうぶ学園〉では、利用者だけで完結するものは主に「アート」として保存し、職員と利用者とが協働でつくるものを「クラフト」と位置づけ、各工房ごとに企画して制作を行っている。
「土の工房」では、オブジェやお面といったアート作品を制作するとともに、職員が成型した器に利用者が絵付けした食器などをクラフトとして販売。収入は各工房で管理して、それぞれの活動費にあてている。
各工房が独立採算制で動いているから、「和紙/造形の工房」に絵を描いてもらった布を、「布の工房」が加工してバッグにするといった工房間のコラボレーションにも受発注が発生する。「土の工房」では、2019年秋に完成した新施設「アムアの森」で使用するタイルの注文を受け、取材時、たくさんのタイルを制作していた。これらのタイルが使われた「アムアの森」の壁や床は、遠くからでも、近づいてもなかなかの存在感。おしゃれでもあり、にぎやかでもあり、学園らしさが凝縮されている。
太い糸や、細い糸、自分のスタイルでオリジナルの世界観を縫い上げる「布の工房」。
学園内でいちばん人数が多いのが「布の工房」。所属は20~25人で、ほとんどの人が刺繍をやっている。
「みなさんそれぞれに特徴があって、全然違うスタイルで作品をつくります。作品を集めてごちゃまぜにしても、どれが誰のものか、すぐにわかるんです」と榎本さん。工房を見てまわると、制作に没頭している人たちの手元には、目を凝らすほど細かいもの、大胆な針遣いのものなど、特徴的な彩りのパターンが縫いこまれていて、各者各様の世界を生み出していた。
設立当初の「布の工房」は、大島紬や刺し子の下請け作業所としてスタートを切ったが、1988年に下請け作業を撤廃して、オリジナル作品づくりへと転向。「針一本で縫い続ける」という行為から生まれる思いがけない表現を大切にした「nui project」を始動した1992年以降は、利用者それぞれのスタイルが光る刺繍作品を発表している。
「ほとんどの方は、刺繍を始めて1〜2年くらいしたら、自分のスタイルを見つける方が多いです。見つけたら、ほとんどのかたがそのままのスタイル。目が悪くなるといった身体的な理由で糸が太くなったり、糸の色が派手になったりすることはありますが、だいたいは変わらないですね」と榎本さん。
「nui project」開始当初から所属する人もいるので、刺繍歴30年のベテラン選手もいるという。
「色や素材、大きさの好みは利用者さんによって違います。職員がさまざまな色や太さの糸を小分けに巻き直して、利用者に好きな糸、布を選んでもらい、自由に制作してもらいます。その後、できた作品をどのように商品化するかを職員が考えます」 1日で終わる人もいれば、5年かけて1枚のシャツに刺繍する人もいる。
机のかたすみに積み上げられた、ピンクと青の毛糸が目に止まった。
「この方は、刺繍をしたあと布のうしろ側で切った毛糸を積み上げているんです。作品のようにきれいですよね。私たちも大好きで、そのまま残しています」という工房の職員も、利用者たちと一緒に作品がつくられる過程を楽しんでいるのだろう。偶然生まれた一瞬のきらめきも、慈しみながらすくい上げている。


工房の奥にある個室では、男性がひとり黙々と赤い布に糸を通していた。その糸は机の上から床へだらりと垂れ下がり、部屋の先まで長く続いている。切った布を一編ずつ縫っているという。昨日はあちらの一編、今日はこちらの一編というように部屋を移動しながら小さな布を4編縫い続けていく。
「吉本篤史さんは、年始から年末まで、この部屋でこうして布を縫い付けています。他の利用者さんが足を引っ掛けてしまうと危ないので、部屋からでないことが条件。その作業は終わりがないので、ご本人さんが実家に帰宅されるお正月休みに勝手に片付けています。そして1月からまた新しく制作が始まります。それを10年間続けています」と榎本さん。
ほかの利用者の制作物は作品になったりクラフトになったりするが、吉本さんのものはそのどちらにもなることはない。一度、美術館で展覧会をやったとき、インスタレーションとして部屋をそのまま再現して展示をしたことはあるという。形には残らなくても、はっとさせられ、見た人の記憶に刻み込まれていくのだろう。「nui project」には、いろいろな表現活動があることがわかる。
点や線、色が踊る絵画や立体作品、風合いある和紙制作に取り組む「和紙/絵画造形の工房」。
建物の中に入ったとたん、あふれんばかりの色彩が目に飛び込んできた。 「壁やら床やらに描いたのは濱田幹雄さんという利用者。描くスピードがとても早いので、描く場所がなくなって、床やドア、シンク、天井などにもペインティングしているんです」と、榎本さんは朗らかに笑う。

大胆な筆使いでテンポよく描き進める濱田幹雄さん。

「和紙/絵画造形の工房」の建物は3つの部屋に分かれている。真ん中の部屋は、シルクスクリーン制作と大きい絵画を描くための部屋。その両隣が、それぞれ和紙をつくる部屋、絵画造形の部屋となっている。ほかの工房と一緒で、自由制作が基本。利用者は、職員が用意したいろいろな素材を選んで、好きなように表現する。
和紙の原料は楮と雁皮。これらを煮出して撹拌、細かくしたものに水とのりをまぜて和紙をつくる。
「和紙職人がやるような、溶液のなかで木枠を揺すって行なう紙漉きは利用者さんには難しいので、木枠に溶液をかける方法で作っています。 この工房も「木の工房」同様、手順や方法を変え、新たな道具を用いることで、“できる環境”をつくりだす工夫をしています。利用者さんが好きでやっていることは変えずに、環境を整えることで、強みを生み出せるよう職員が工夫する。これが “しょうぶメソッド”として、日々施設長から職員に求められている課題です」


取材時、絵画造形の部屋では、施設内の「Sギャラリー」で利用者のペイントを施した手描きTシャツを販売する「工房しょうぶ 手描きのTシャツ展」(2019年7〜8月開催)のための製作が行われていた。見ていると、ほとんどの人が迷いなくさくさくとペンや絵筆を動かしている。描き終わった人は、違うことをしたり、昼寝をしたり、音楽を聞いたり。自由な雰囲気が心地よい。
BGMはハワイのアーティストの音楽が流れていた。「いつも音楽のセレクトは、は隅谷端さん。クラシックやビートルズが多いのですが、マニアックなアーティストを見つけてきてかけてくれることもあります。気持ちいいですよ」と榎本さん。しょうぶ学園職員の名刺は、味のある手描き文字が上手な隅谷さんに描いてもらっているという。
利用者と職員、それぞれが刺激しあい、それぞれに影響を与えあいながら行われるものづくりの現場。
4つの工房で制作風景を見学して話を聞くほどに、それぞれの特性が魅力となった作品・製品づくりは、簡単にできるものではないことがよくわかった。そこにいたるまでは職員による創意工夫があったからこそ〈しょうぶ学園〉らしさが生まれている。
利用者にいろいろな個性があるように、職員にだってそれぞれ個性がある。 そうした個性同士が補い合い、工夫をしながら、良いところを伸ばしているからこそ、多様性がおもしろく活かされる。
「“自分らしさ”って、利用者より私たちのほうがわからなかったりするから、もどかしく感じることもあります」と榎本さんはいう。
「今まで受けた教育とか、正しさとか、かっこよさとかの概念にとらわれているから、私たちは“自分らしさ”の殻がなかなか破れない。だから利用者さんのほうがわかっていますよね。自分はなにがしたいのか、なににうれしくて、心地良いと感じるのかを。ひるがえって私たちは、そうしたことを本当にわかっていないことも感じることが多くあります。利用者さんたちを見ていると考えるきっかけにもなるし、利用者さんから教えてもらうことも多くあります」。
榎本さんが〈しょうぶ学園〉を初めて訪れたのは10年ほど前。アメリカで絵の勉強をしていたもののスランプになり、なにをどのように描いていいかわからなかった状態のとき。 「私はアーティスト(表現する人)になりたかったのですが、迷いがあって、絵を買ってくれる人が欲するものを描いた。だから〈しょうぶ学園〉の利用者さんたちの表現を見て、すごくショックでした。自分はアーティストって名乗っちゃいけないと思いました」。その後、榎本さんは〈しょうぶ学園〉で働き始め、しばらくの間、自分の制作をやめていたが、最近、ようやく「描きたい」という気持ちがわいてきたという。
「利用者さんの制作を見ていると、プランをしないんです。画用紙を前にすると、私はどういう構図で、どんな色を使おうか、まず考える。でも、彼らは画用紙を渡したらすぐに筆をおろす。かなわないなぁって思います(笑)。最初の頃はうらやましくてしかたなかったのですが、今は私がそうなるのは無理だとわかったので、私は私にできることをやるしかないと思うようになりました」と楽しそうに話す。
それぞれが刺激しあい、それぞれに影響を与えあう関係性。〈しょうぶ学園〉には、障害のあるなし関わらず、ものづくりをする人たちにとって理想的な環境が、日々の創造と工夫の中でつくられている。
――後編では、こうした〈しょうぶ学園〉らしいものづくりが、どのようにして生まれてきたか。福森伸統括施設長に振り返ってもらいました。
取材/2019年7月
◯Information
〈しょうぶ学園〉
鹿児島県鹿児島市吉野町5066
電話:099-243-6639
https://www.shobu.jp/