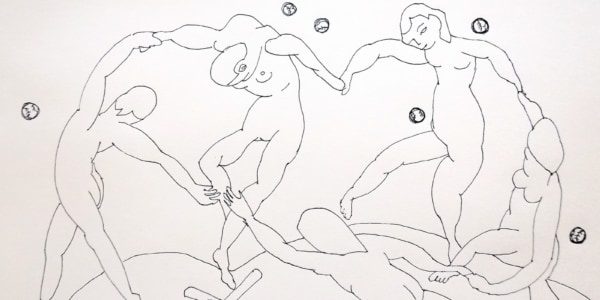「月曜美術館」は存在する?アートは見ている側にこそ、創造的なものが求められる
ヘッドドレスを身につけることがアートであり、歩く展覧会とおっしゃっていますね。
ヴィヴィアン)
頭上建築とかね(笑)。こういうのを被ることって、都会における失われた呪術性、モダン・プリミティ的な考えを獲得することになるのだと思っています。
ヴィヴィアンさんが歩くことで多くの人が振り返り、アートと鑑賞者の関係ができあがっていました。
ヴィヴィアン)
鑑賞者が対峙しないとアートは存在し得ないという美術論があるのではないか。「日曜美術館」ではなく「月曜美術館」が成り立つかどうか。休館が多い月曜日の美術館にアートは存在しているかという話。もちろん閉館している深夜にだってアート作品はあります。でも、やっぱり鑑賞者がいることで初めてアートは存在すると思うのです。
私、映画評論の仕事をよくしているのですが、作品自体はぶっちゃけつまらなくていい(笑)。映画は映画監督のものでもプロデューサーのものでもない。むしろ彼らが思いもしなかった見かたを鑑賞者はしてもいい。駄作であればあるほど、それをどういうふうに深読みするか、豊かに誤読するか。間違ったっていい。間違いはない。それを自分の言葉でいかに語れるか。だから、彼らより深く理解して、気づかない文脈を発掘してあげることで、その作品を監督やプロデューサーから奪うことだってできちゃう。
作品を与えられるだけでなく、鑑賞者もまたアーティストとなる。
ヴィヴィアン)
たとえば、20歳の子だったらば、そこにいたるまで、まったく同じ経験をして育ってきた人なんて、いないわけですよね。双子ですら全く違う人格で、違う経験をして生きてきているわけだから。それぞれに固有の体験をもっているそれぞれの人間がある作品を前にしたときに、自分の今までのことをどう照らし合わせて、どう感じるか。それをどう自分の言葉で語るかというところまでいくと、実は見ている側、鑑賞者や批評家のほうが、創造的なものが求められるのではないかという考え方です。
つくり手と鑑賞者は対立するのではなく入れ替わるし、パワーバランスだって崩れる。結局は同じ立場じゃないかと思うのです。

批評を超えてしまう「理由を問えない作品」があったっていい
映画であっても、作品であっても、見る側の想像力を刺激するもの、そうでないものはありませんか?
ヴィヴィアン)
確かにそういうのもあるかもね。映画でいえば、芸術であるけれど同時に興行でもある。監督やプロデューサー、俳優は、1週間でどう売るかを考え、自分たちの作品をどう見てほしいかを伝える。「ネタバレ注意です」みたいなこともいわれるけど、そんなこと、はっきり言ってどうでもよくて、黙っててって! 思うくらい(笑)。
アートって受け取り方も、成長のさせかたもさまざま。同じ1本の映画でも、先週見て、今日見て、5年後、10年後にまた見たら全然違う。映画自体は変わらないけれど、こっちが毎日生まれ変わっている。だから先ほどの「月曜美術館」のように、作品は見ている人がいて初めて存在するし、輝きだすものだと思うのです。
障害のある人のアートにおいても、コミュニケーションや生活のなかで生まれるものが多いように感じます。
ヴィヴィアン)
「理由を問えない作品」ってあってもいいと思っています。批評を超えてしまうような。「これはなんですか?」って作者に聞いたうえで、理詰めで考えておもしろいものもある。
でも、未解決事件の誘拐犯による脅迫文って名文といわれているものが多くて、そうしたもののように、それ以上問えないことってあるじゃないですか。分解も解説もできない。だけれども切実ななにかがある。そういう作品ってアートにはありますよ。
ヘッドドレスは生き様であると同時に、普段見えないもの、感じないことをキャッチできるアンテナでもある
「お化粧やヘッドドレスをしていると、アートや映画の見かたが変わってくる」と、ヴィヴィアンさんはおっしゃっています。それは作品と鑑賞者が鏡のような関係性だからでしょうか?
ヴィヴィアン)
お化粧やヘッドドレスで着飾ることって、ひとつには呪術的な意味合いがある。化粧して着飾ると、違う自分になれるから楽しいって、渋谷でハロウィンをしている若者たちはよく言っているけど、むしろどんどん裸になる行為。
お化粧すればするほど裸になって、それを通り越すと皮膚が裏返しになって内臓まで出てしまう。変身ではなく、戻ることがお化粧するという行為の根本にある。ヘッドドレスもそう。荒れ狂った内面がちょっとだけ表に見えるにすぎないのです。

呪術的な意味合いがあるというのは、それが「戻る行為」だから?
ヴィヴィアン)
たとえばフランスのマリー・アントワネットの髪型、日本でいうと花魁の伊達兵庫などもそうだし、お雛様のような公家の髪型もそう。古今東西の民族衣装もドラァグクイーンも、バブル期にお立ち台に上っていた女の子の髪型も、戦国武士の甲冑もそう。みんな同じ役割だと思うのです。戦国時代は今の戦争とは考え方や作法が違って、戦場であえて能を舞うことが大切だったりするじゃないですか。いまじゃ意味がわからないけど(笑)。
戦場であのような目立つ格好する必要も、能を舞う必要もない。つまりは生き様の問題だったのでしょうね。ヘッドドレスも同じく生き様であるとともに、普段見えないもの、感じないことをキャッチしたり、絡め取ったりするアンテナであり網でもある。
だからヘッドドレスをつけて映画館や美術館にいくと、見えるものが変わってきますよ。街中を歩いていてもそう。でも、今まで見えていなかったものが見えるようになるけど、今まで見えているものは見えなくなる。普通の人に気づかなくなるとか、つまずきやすくなるとか(笑)。
広がるのではなくシフトする。
ヴィヴィアン)
そう単純な話。そして、呪術的な意味合いでいうと、普段見えないもの、感じないもの、人間以外のものたちと交流するツールのような役割もあったと思います。武将が身につける甲冑や銀座のマダムのコスチュームは、自分とは違う身分や立場、職業の人とやり合うためのツールでもあったけれども、だんだんともともとあった呪術的な役割や目的が薄れて機能しなくなってきている。
けれども、例えばやっぱりタトゥーで皮膚になにか彫りたい、派手に着飾りたい、店の壁になにかを描きたいって、失われた本能をちょっと取り戻したいという気持ちが残っているように感じます。それを暫定的に、ファッション、アート、音楽という言葉で名付けて満たそうとしている。

ヘッドドレスは本能的なものに触れるもの。つくっていくうちに、自分の欲望と向き合える
たしかに、ダンスも音楽もアートも本能的な部分が垣間見えます。
ヴィヴィアン)
すべては意味があって目的があった。でも今はそういう時代ではない。そう考えると、アートは「人工」で「偽物」なんです。建築にしても、どこかの集落で信じられているもの、言い伝えのなかから自然発生的に生まれたもののほうが「正解」なのです。だから、アートは自然発生的なものと対峙したら負けるもの。だって「偽物」だから。でも、負けることが悪いのではなくて、「いかにちゃんと負けるか」が存在意義だと思うのです。
だから、私のヘッドドレスも偽物ですよ。民族衣装からしてみれば。でも、そうしたものと対峙したときに呼応して、ちゃんと負けるというのが理想。本物にはかないませんからね。
お化粧をしたり、ヘッドドレスをつけることで内面が出てくると考えるのも、すればするほど原始に戻っていく、本能的な部分へと近づいていくということでしょうか?
ヴィヴィアン)
お化粧やヘッドドレスは、そうした本能的なものやそれを信じていた人類の経験の瞬間に触れることだと思っています。本当はね。だから、ヘッドドレスのワークショップでヘッドドレスをつくっていると、最初は「ファッション」としてやりたいと思っている人が多いのですけど、やっていくうちにそのことに気づいてくるのですよね。
ヘッドドレスワークショップって6時間くらいかけて、つくっていくのです。とても長いのですよ(笑)。でも、その間に自分の内面が出てくる。どうしたいか、自分の欲望と向き合うわけですね。
社会の中で名付けられない立場として存在することが、ドラァグクイーンの存在意義のひとつ

ヴィヴィアンさんは、日頃から「人と人との空気をかき回して、性差やファッション、建築、アートなどの垣根を取り払っていきたい」と発言されています。ワークショップもそのひとつ?
ヴィヴィアン)
「ドラァグ」には引きずるという意味があって、長いドレスを引きずって現れるから「ドラァグクイーン」はそう名付けられたのだけど、もうひとつパーティーの雰囲気をかき回して牽引するという意味合いもあると思うのですよ。
日本では80〜90年代くらいから『ロッキー・ホラー・ショー』とか、あのあたりと一緒に入ってきた言葉ですが、古今東西、そういう考え方は昔からあったのです。
たとえば、スーザン・ソンタグというアメリカの哲学者であり社会運動家が1968年に『《キャンプ》についてのノート』というエッセイで、キャンプについて考えています。不自然で、人工的、誇張されたものであり、とらえどころのない感覚でもあるキャンプは、オスカー・ワイルドやデヴィッド・ボウイもそうだと定義していくのです。
それ以前にも言い方は違えどもキャンプという考え方はあって、17世紀ベラスケスの絵画には宮廷の中で王族と一緒に小人症の人や占い師などが描かれています。
当時、宮廷の中にも、名づけられない、分類できないような人たちがいました。一般の国民は王族に直接謁見できないし、話しかけることもできないけれど、そうした社会の身分に収まらない人たちが宮廷の中にいて、遊び相手になったり、アドバイスをしたりする。
ドラァグクイーンはそれに近い存在かなと思っています。ドレスアップはひとつのアイコンでしかなくて、こうして社会の中で名付けられない立場として存在することが、ドラァグクイーンの存在意義なのかなと思っています。


写真提供:ヴィヴィアン佐藤

写真提供:ヴィヴィアン佐藤
「名付けられない役割」
「名付けられない時間」
「名付けられない性別」
を日常で表出する
ところで、ヘッドドレスのワークショップをやりはじめたのはいつごろで、どんな経緯で?
ヴィヴィアン)
ま、ひとくちにいうと、需要があったからでしょうね。ひとり一人のなかにも名付けられない感情とか、名付けられない部分ってあって、そういうのをどうしたって出す必要がある。
ワークショップをやってよく聞かれるのが、ヘッドドレスをいつつけたらいいか、どういう場面で? という質問。ワークショップに来たけど、つくっている人すら、それがわからない。けれども、CD聞きたいけど、いつ聞けばいいかわからないから買いませんという人はいないですよね? 要するに、それぞれのなかで「名付けられない時間」とか、「名付けられない空間」をつくることが大切なのですよ。それがワークショップの目的のひとつ。
社会で生きていると、なにかと役割を求められるから、その煩わしさと、そこからはずれる怖さがある。でも、「名付けられない」自分でいたいときもある。
ヴィヴィアン)
ほんと、ヘッドドレスは象徴的なものかもしれないですね。名付けられない役割、名付けられない時間を日常の中で表に出していくことがワークショップの目的のひとつです。
そしてモダン・プリミティブで、呪術的、失われてしまった本能でもある。
ヴィヴィアン)
たとえば今、ほとんど会議も、会社も、例えばライブも、演劇も、大学の授業も、飲み会も、すべてオンラインに置き換わっている。テレビは見れば見るほどひとつの価値観に凝り固まっているし、インターネットで検索したらわかった気になってしまう。でも、テレビにない価値観、ネットにのってない側面も見ていかないといけない。すぐに得られる情報って非常に強い権力をもっている。
みんな気づかないけど、それはすごく恐ろしいことだと思うのです。たったひとつの側面であり、広い面だけが重要とはかぎらない。世界はインターネットでは決して置き換えられませんから。

photo:T,Obara
写真提供:ヴィヴィアン佐藤
世の中にはたくさんのマイノリティがある。実際にマイノリティになることで、多様な生き方や価値観にふれる
日本全国各地で、ヘッドドレスワークショップをしていますね。
ヴィヴィアン)
町おこしのように地域に呼ばれて行くとき、映画のこともやるのですが、子どもたちをドラァグクイーンにさせるというワークショップもやっています。
青森県・七戸では、初年度は一軒家を借りて滞在しながら10カ月間、毎日勉強会とか講演会、農作業の手伝いとかしながら、ワークショップをやりました。ヘッドドレスをかぶることで、子どもたちをマイノリティーにするのです。
子どもたちをマイノリティにするって、おもしろい。
ヴィヴィアン)
世の中にはセクシャルマイノリティだけではなくて、あらゆるマイノリティがいます。ノイズミュージックが好きでたまらないけど、学校の先生も兄弟もわかってくれないというマイノリティだっています。
そういう子たちに、たとえばこういう生き方もあるし、こういう価値観もあるのだよということを教えてあげる。

photo:T,Obara

photo:T,Obara

photo:T,Obara

photo:T,Obara
人と地域、本人や土地の人も知らない潜在的な魅力が二重に引き出されている
すごくいい写真です。
ヴィヴィアン)
観光地ではない、地域の人しかわからないような場所、でも土地の人なら馴染み深い場所で撮影します。
子どもたちがかわいいのは、お化粧したり、ヘッドドレスをかぶったり、衣装を着ているからではありません。4歳から15歳ぐらいまでの子どもたちを撮っているのですが、彼らが生まれてからこれまで出したことのないような側面とか在り方が、お化粧や着飾ることで少しせり出してくるのです。子どもたち自身も、もちろん親も知らないような側面がでて、どんどん裸になっていきました。
地域の風景も際立っています。
ヴィヴィアン)
こうした子どもたちの存在によって、普段見えてこない地域の魅力も出てきたのです。
ここでは二重の反転が起きています。潜在的に持っている子どもたちの側面が、お化粧や着飾ることで出てきて、さらには潜在的な地域の魅力が、子どもたちがいることで裏返しになり露出してくる。
だから、まちおこしも、人の隠れた面を出すことも、同じことだと思っています。もともとある人の魅力と一緒に、土地の良さも再認識して、知ってもらうことができました。
ワークショップは全国でやっています。2020年11月は、愛媛県松山で子どもたち50人と一緒にやりました。
マイノリティになってみることは、多くの人が体験するといいですね。
ヴィヴィアン)
みんなマイノリティですよ。
なるほど、そのことに気づくのこそが大切。
ヴィヴィアン)
だから、誤解を恐れずに言うと、「私はLGBT反対派」ですから。こんなことをいうと、怒られますけどね(笑)。
要するに、LGBTという言葉がなくなることが最終目標なのです。だから、あなたがLで、あなたがGで、BでTっていうふうに分類することは意味がないことだと思っています。