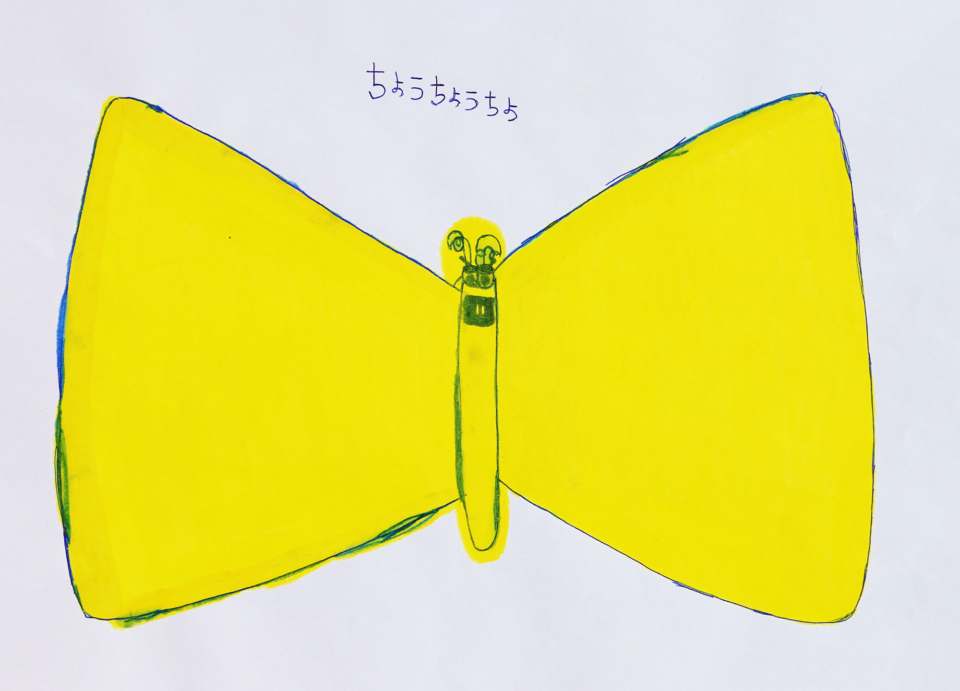生きる術としてのアートが、
日常の真ん中にあるということ
大昔、職業という概念が存在しない時代、人はみな踊り、歌い、作る人だった。日常的行為として、アートは人々の真ん中に存在していた。そもそもアートの語源は、ラテン語のアルス「ars」。それは術、才能などを指しているが、当時の人々にとってアートはまさに、生きるための術だったはず。その後、文明の進歩に合わせて職業や役割が生まれ、アートもまた、大半の人々の日常から遠ざかっていくまでは。

6つのグループがある〈やまなみ工房〉。そのうちの一つ、〈アトリエころぼっくる〉では、粘土や絵画を中心に、日々さまざまな経験を積んでいる。


男性が多い〈アトリエころぼっくる〉に対して、スタッフも利用者も女性という、スタジオ〈こっとん〉。毎日刺繍や刺し子、織りや絵画などをしながら、女子トークにも花を咲かせる。

敷地内には利用者の作品を鑑賞できる〈ギャラリーgufguf〉や、ランチもできる喫茶店〈Café hughug〉があることから、外からの見学者も多く、工房全体がオープンな印象。
滋賀県と三重県の県境、甲南町にある、アート活動を中心とした福祉事業所〈やまなみ工房〉に訪れた。現在、この工房では自閉症や知的障害を持つ81名のアーティスト(利用者)と22名のスタッフが共に過ごし、さまざまな創作を行っている。散歩、古紙回収、お菓子作り、スポーツ、敷地内の喫茶店での接客などといった活動がある中で、利用者一人ひとりが何をどう過ごしたいのかを見極め、尊重していく環境がここにはある。
一人の利用者の笑顔が、施設を変える
好きな色の布の一面にボタンを縫い付けながら、それが終わると丸めて球状に縫い留める人。割り箸を使って、規則正しく一定の間隔を保ちながら、粘土に点を刻んでいく人。寝転がり肩肘付きながら、墨汁と割り箸1本で人物を描く人……。自分の内側から湧き上がる欲求の先にアートが存在する彼らの姿を垣間見ながら、私はいつしか大昔の人々の日常と重ねてみていた。生きる術としてのアート。やまなみ工房にはそれが存在しているように思えたのだ。
「僕たちスタッフは彼らがいかに日常を自分らしく過ごせるかに目的を置いて日々活動をしています。その結果としてのアートであって、アートが目的ではないのです。だから僕自身、正直彼らの作品に芸術的価値があるかどうかということは、あまりよくわかっていないという自覚が今でもあります。一人の人間が絵を描きました。その絵はすごく不思議で魅力的です。たまたま障害を持っていました。こんなにブレずに一つのことをやり続けているおもしろい人がいます。だから知って欲しい。そんな想いのもと、彼らの作品を社会に発信していった先に、芸術的価値を見出してくれた方々がいたんです」

施設長の山下完和さん。もともと福祉やアートに全く興味がなかったという山下さんは、友人が、〈やまなみ共同作業所〉の職員だったことをきっかけに、ここの支援員となった。
こう語る山下完和さんは、1986年に3人が利用する通所の作業所として出発した〈やまなみ共同作業所〉に1989年、支援員として就職。現在は〈やまなみ工房〉の施設長として、利用者に寄り添う毎日だ。山下さんが就職した当時の〈やまなみ共同作業所〉は、障害者の経済的自立を第一の目的として、みんなが同じ空間で同じ内職作業を行っていたという。それが今のような個性を大切にしたアート施設へと方向転換したのは、ひとりの利用者の笑顔がきっかけだった。
「その当時、三井啓吾さんという一人の男性が〈やまなみ工房〉にやってきました。三井さんは重度の障害を持っているので、自分の言葉で想いを伝えることがなかなかできませんでした。そのためこちらがお願いした通りに黙々と内職をしていたのですが、ある日のお昼休みにメモ用紙の端くれを拾った三井さんが、傍にある鉛筆で何やら描き始めてたんです。そのときの三井さんの表情がもう本当に楽しそうで嬉しそうで。1年以上一緒にいたにもかかわらず、そんな表情は初めて見ました。そのとき思いました。こんないい表情ができるのに、それを引き出せない内職をこなすだけの日常は一体なんだろうと。それからというもの、一人ひとりが本当に望むことをこの作業所でできないだろうか?と模索し始めました。そして彼ら全員にいろんな体験をしてもらうことにしたんです。その中で、やっぱり三井さんは粘土を触ったり絵を描くときにいきいきとした笑顔を見せてくれたんです」


この経験が、粘土や絵画を中心に創作活動を行う場所、〈アトリエころぼっくる〉の誕生のきっかけにつながっていく。その後も個の輝きが放たれるようにと、利用者それぞれの個性を受け止める場所として、6つのグループに分けた活動場所を工房内に完成。それぞれの場所で日々増え続ける作品は、やがて1994年にエイブル・アート 01 提唱者、播磨靖夫氏に発見されることで、広く社会に向けて発表する場が生まれていく。
「やまなみ工房で彼らの創作活動を始めた当時は、それが社会の中ですぐに対価へと結びつくことは難しく、それ以前に創作行為そのものにも、光を当てられることはありませんでした。こんなことをしても意味はないといった批判的な意見もありましたが、人生は一度きり、結局最後は彼ら自身がやりたいことをやるべきだというところに立ち返るんです。その葛藤の中で、播磨さんが彼らの行為に価値を見出してくださって、さらなる活動へと繋がっていきました」
この積み重ねによって、徐々に彼らの作品に対する認知度が高まり、現在やまなみの工房に併設されている〈ギャラリーgufguf〉には、全国から4年間で1万人を超える人が訪れる場所になった。同時に国内外の美術館やギャラリーでも高く評価され、スイス「アールブリュットコレクション」やフランス「ABCDコレクション」、アメリカ「ケヴィンモリスギャラリー」、イギリス「ミュージアム オブ エブリシング」など、世界的に著名なコレクションにも作品が収蔵されている。

〈ギャラリーgufguf〉では年4回、〈やまなみ工房〉のアーティストを始め、国内外のアーティストの作品による展覧会を行っている。
「福祉が福祉施設の中ですべてを完結しようとするのは、よくないことだと僕は思っています。だからこそ、いろんなプロフェッショナルな人たちが彼らと対等にコラボレーションすることによって、作品の魅力が正しく伝わっていくのであればできる限り参加したいですし、発信していきたいと思って活動しています。何より障害者の作品ではなく、アートとして評価される。それは彼らが個として社会にかかわっていることだから、純粋に嬉しいですね」
世界的に注目される施設になった今でも、山下さんをはじめ、やまなみ工房には美術の専門的な教育を受けたスタッフはいない。当然、彼らの表現活動に口出しをしたり、手出しすることも一切ない。あくまでも彼らが描きたいと思う場や空気を整えることに集中している。それは山下さんが常に心に留めていることがあるからだ。
「どんなに社会から彼らの作品が賞賛を浴びようとも、彼らがそれを作りたくないと言えば、それは作らなくていいんです」
ラーメンの袋を握って見つめて20年
〈ギャラリーgufguf〉の隣に併設された〈Café hughug〉でお茶をいただいていたら、鮮やかなピンク色のスウェットを着たショートカットの女性がこちらに向かってくる。顔の正面にあげた両手には何か袋を握りしめていて最初はそれが何かはわからなかったが、次第に彼女が近づくにつれてその袋がインスタントラーメン「サッポロ一番」のパッケージだとわかった。彼女の名は、酒井美穂子さん。利用者の一人だ。ラーメンの袋を見つめて20年になるという酒井さんは〈Café hughug〉へお茶をするために来た。
「たとえば体温、食欲、目つき。僕たちスタッフは利用者の方たちの想いをいろんなところで日々読み取っています。その象徴とも言えるのが、ラーメンの袋を片時も離さない酒井さんですね。そんなことをずっとしていてどうするの?というのが僕自身の概念としてまずあるから、その袋を酒井さんの手から取ってペンを渡してみたり、いろいろ試みたのですが、逆に彼女は苛立ち不安定になりました。やがて僕も根負けして、ラーメンの袋を持ち続けることで、酒井さんが落ち着くならいつまでも持っていていいよと思ったんです」


起きている間は、ずっとラーメンの袋を手にしているという酒井美穂子さん。
酒井さんは、このサッポロ一番の袋を両手で持ち、中の乾いた麺の形を確かめるように触り続けている。お母さんに家から持たせてもらったラーメンを“使い終わる”(どこが終わりなのかは、本人にしかわからない)と、また新しいものに取り替える。酒井さんがこのラーメンを食べることはない代わりに、やまなみ工房では使用済みのサッポロ一番を作品として棚に保管し続けているという。
人は多様だ。当然、自分の正解が相手の正解だとは限らない。でもだからといって、そこで多様だねと言い切って整理してしまうのは、思考停止のような気がしてどこか違和感を覚える。私とあなたは違う。違うけれど、でも、それでもあなたを知りたいという姿勢、コミュニケーションこそが、本当の意味での多様性の中を生きることにつながるのではないか。やまなみ工房での時間は、私にとってそういう時間になった。
「先ほど僕は、彼らの作品に芸術的価値があるかどうかよくわかっていないと言いましたが、僕は彼ら一人ひとりに対する憧れや情がありすぎて、そもそもまっすぐ作品が見れていないだけなのかもしれません」
いわゆる美術の技法や方法論からは生まれてこない彼らの作品には、本質的にはメッセージはない。ゆえに私たち観る側が作品を鑑賞した瞬間に何を受け取り、何を感じるのかによって作品の表情は自在に変わっていく。感じかたは生き方だ。私たち自身の生き方もまた、作品を通して問われるような気がした。


Information
やまなみ工房
〒520-3321
滋賀県甲賀市甲南町葛木872番地(ハートヘルスパーク甲南内)
TEL : 0748-86-0334
やまなみ工房ウェブサイト